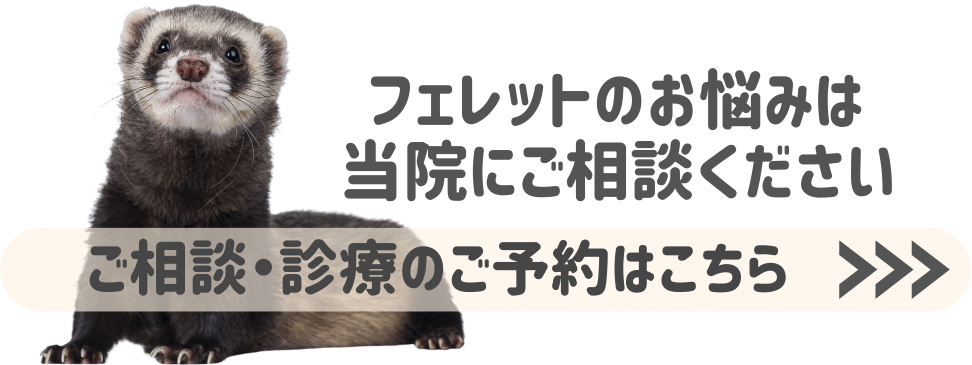フェレットの副腎腫瘍
フェレットの副腎腫瘍について
川崎市、多摩市、横浜市、稲城市、大田区、目黒区、世田谷区の皆さんこんにちは。
川崎市高津区のくらた動物病院院長の倉田英樹です。
今回は、フェレットによく見られる副腎腫瘍について詳しく解説します。
2024.07.29最終更新
副腎腫瘍とは
フェレットの副腎腫瘍は非常に一般的な疾患であり、私が診療を始めた1995年頃から、その傾向は変わっていません。
興味深いことに、犬や猫の副腎腫瘍の場合とフェレットの副腎腫瘍の場合では、現れる臨床症状は大きく異なります。
症状
フェレットの副腎腫瘍の主な症状は、腫瘍から分泌される性ホルモンによって引き起こされます。
・脱毛(正確には発毛不全):最も一般的な症状
・メスの外陰部、乳腺の腫脹
・オスの乳腺腫脹
・その他、体臭の増加、マーキング、性的行動の増加など
オスでは前立腺肥大や前立腺周囲嚢胞による排尿障害が副腎腫瘍に関連した症状として認められる場合もあります。
症状において注意すべき点は、症状の程度と腫瘍の大きさは必ずしも比例しないということです。
また腫瘍組織の存在そのものによって引き起こされる症状としては
大型化した腫瘍組織が原因で隣接する後大静脈が物理的に圧迫されたり、腫瘍組織が後大静脈内に侵入して腫瘍栓を形成することで血流が妨げられ、循環不全が生じます。
特に左副腎腫瘍が後大静脈内に腫瘍栓を形成すると、急速かつ重度の腎不全を引き起こすことがあります。
また、稀に突然死を引き起こすこともあります。
発生要因
主な要因は、春から秋にかけて脳から分泌される性腺刺激ホルモンが、通常の標的である睾丸や卵巣の代わりに副腎に作用することで、副腎の組織から大量の性ホルモン分泌が始まります。また大量のホルモンを出すために、組織が発達し、腫瘍化に繋がるとされています。
しかしながら、この説では未避妊・未去勢のフェレットにも副腎腫瘍が発生する場合があることを説明できず、未知の原因がある可能性が示唆されます。
治療方法
a) 内科的治療
当院では多くの症例で最初に選択される治療法です。月に一回酢酸リュープロレリン(商品名リュープリン)を皮下注射で投与し、副腎腫瘍からの性ホルモンの分泌を抑制します。
症状は改善しますが、副腎腫瘍は残るため、定期的な腫瘍の大きさのチェックが必須です。
メラトニンの投与に関しては、その治療効果が長期間維持できないことを裏付ける文献があるため、当院では採用していません。
b) 外科的治療
開腹手術で腫瘍を摘出します。通常、腫瘍を含む副腎全体を摘出しますが、もう一方の副腎が正常であれば問題ありません。
以下のケースでは手術をお勧めします:
①副腎腫瘍が左右どちらか片側だけに発生している場合
②リュープリン治療中に腫瘍に明らかな増大傾向がみられる場合
③最初の診察時に腫瘍が1cm前後まで大型化している場合
④両側の副腎腫瘍が発生している場合において、片側の副腎腫瘍が急速に増大してきた場合
数センチ以上の大きさに増大した副腎腫瘍でも、多くの場合において手術をすることは可能です。
最近の傾向として、他院でリュープリン治療を受けていたフェレットが腫瘍の増大により当院に転院し、大型化した副腎腫瘍の摘出手術を実施することが増加しています。
しかし大型化した副腎腫瘍では、手術の難易度は増加します。

最近の治療の考え方について
フェレットの副腎腫瘍治療において、従来は内科療法のリュープリン注射を初期治療とし、腫瘍増大時に摘出手術を行うのが一般的でした。
しかし、当院では最近、副腎腫瘍発見時に摘出手術を第一選択とし、反対側の副腎腫瘍化時にリュープリン治療を行う方針を提案しています。
フェレットの副腎腫瘍治療において、1997年にリュープリン治療を導入した当初は、手術不適合例や片側副腎摘出後の症例に使用する次善の策でした。外科的摘出が第一選択でした。
しかし、リュープリン投与による臨床症状の改善効果が高く、副腎腫瘍の増大が通常緩徐であることから、次第にリュープリン治療が第一選択となりました。
約25年の治療経験の中で、稀ではありますが、リュープリン治療中に腫瘍が急速に大型化するケースに遭遇しました。そのような症例では、高齢による合併症で手術リスクが高くなったり、腫瘍の急速な浸潤で摘出が不可能になったりして、腫瘍自体が死因となることもありました。
これらの事態は、副腎腫瘍の診断初期に摘出手術を行っていれば回避できた可能性があります。副腎腫瘍が急速に増大する可能性は低いものの、その可能性や時期を事前に予測することは不可能です。
そのため、フェレットの副腎腫瘍治療において、手術が可能な条件を満たす限り、積極的に外科的摘出を第一選択として当院では、お勧めします。
この方針により、将来的な合併症や手術が不可能な状態に陥るリスクを最小限に抑えることができると考えています。
手術後の反対側の腫瘍化について
手術後、反対側の副腎が腫瘍化することがあります。
その時点での外科的摘出は適応外であるため、内科的治療であるリュープリンの注射を実施します。
反対側の腫瘍化に対する予防的治療の考察
リュープリンにはその薬剤の作用機序の観点から副腎腫瘍発生の予防効果がある可能性がありますが、まだ文献的裏付けがありません。
高価な薬剤のため、予防的投与は飼い主様との相談の上で実施しています。
フェレットの副腎腫瘍は複雑な疾患ですが、適切な治療と定期的なチェックで管理可能です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
投稿者: